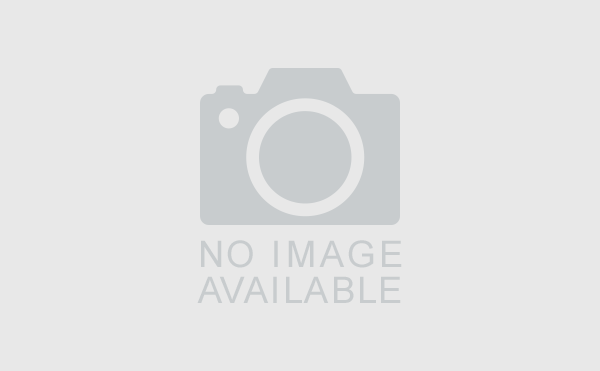臨床看護研究の進め方:事例研究の進め方
研究でエビデンスを生み出す過程は、すべてがひとつひとつの個々の研究から始まります。その研究のひとつに事例研究があります。事例研究それひとつだけでは、臨床実践に強烈なインパクトを与えることはあまりありませんが、看護学研究は現象を記述することから始まるため、個別の事例を言語化していくことは非常に重要です。
看護学研究における個別事例の報告は、医学研究における症例報告に似ています。医師が報告する症例報告は、例えばガイドラインから逸脱した症例に対し、特異的な治療や対処をし、その過程や結果を報告します。こうした報告が蓄積されることで、新たな治療や対処のカギが見つかり、コホート研究やRCTなどの発展的な研究へとつながり、エビデンスの構築に貢献します。看護学研究における事例研究も、こうした事例報告を行うことで、将来の研究や実践につながることが期待されます。そして何より、このような日々の実践の中で得られる事例を扱う研究は、臨床家が得意とする研究のひとつでしょう。
事例研究それ自体、非常に奥深い研究手法で、専門書もたくさんあるくらい、突き詰めれば専門的なスキルを要する研究手法です。ここでは、研究に馴染みのない臨床家が日々の実践を事例研究としてまとめる際のポイントをいくつかかいつまんでお伝えします。
尚、事例研究とはいえ、研究が目指すことや研究疑問(Research question)は、他の研究と同様に重要です。研究全般に関する概要や問いの立て方については、別記事を参考にしてください。
事例研究のポイント1:一般性と特異性
説明をわかりやすくするために、医学研究における症例報告を例に見てみましょう。まず大前提として、症例として報告すべき現象は、ガイドラインや標準的な治療によって、予測可能な一般的治療効果が得られた症例ではあまり意味がありません。すでに多くの医療者がその治療過程や治療結果をわかっているので、みんながすでにわかっている一般的な症例を報告しても、読み手に有益な情報を与えられないためです。別記事で説明しているように、研究とは大なり小なり、新しい知見(新規性)を提供するために行うものです。また、冒頭で触れたように、ガイドラインや標準的な治療は個々の症例報告からスタートしていることがほとんどです(医学や一部の看護学の場合、動物実験などの基礎研究が本当の意味ではスタート地点である)。したがって、そのような一般的な症例は、すでに報告されているため、改めて報告する意義はありません。
では、どのような症例(事例)を報告すべきでしょうか?すでにお分かりかと思いますが、一般的な症例(事例)から逸脱したものを報告することに、大きな意義があります。「一般からの逸脱」は、さまざまな視点でとらえることができます。例えば、ガイドラインや標準治療では対象としていない対象者(=対象者の特異性)、ガイドラインや標準治療では登載されていない治療法(=治療・介入の特異性)、これまで報告されていない治療効果(=結果・アウトカムの特異性)などです。看護学研究における事例研究も同様です。看護において、「Xというケアを行うことで、Yという効果が得られる」といったような、標準的な看護ケアは存在しています。このとき、ケアXを行いYという効果が得られたことを報告しても、すでに看護職であればわかっていることですので、改めてその事例を報告する意義はありません。「効果Yを得るため、標準ケアXではなく、ケアZを行ったところ同様の効果が得られた」などは、新しい知見を提供しうる有益な事例研究となるでしょう。
すなわち、あなたがとある事例を事例研究としてまとめてみたいと思ったとき、まず初めにすべきことは、そのテーマにおいてどのようなことが報告されており、そのテーマを報告する意義があるかどうかを見定めることです(少し極端な言い方をすれば、「そのテーマを報告する価値があるかどうか」と言っても良いかもしれません)。一般的、あるいは標準的なことと、取り扱うテーマの特異性を明確にし、線引きすることです。既知と未知の線引きをする、とも言えます。勘の良い人はお気づきかと思いますが、この「既知と未知の線引き」は、事例研究だけでなく、あらゆる研究を行う上で必要となる作業です。普段目にする量的研究や質的研究のように、対象者数や研究手法が少し違って見えるため、「事例研究は別物」と事例研究を特別視する意見もありますが、そんなことはありません。事例研究も、既知と未知の線引きをし、問いを立て、その問いを解決するような結果を得るという意味で、他の研究と何ら変わりありません。
少し脇道に逸れましたが、事例研究のポイントは、取り扱うテーマが報告する意義があるかどうかを見定めること、そしてそのためには、そのテーマが、ガイドラインや標準的看護、これまで報告されてきたことと異なる点(特異性)を明確にするところからはじまります。この線引きのためには、テーマに関する文献レビューが欠かせません。文献レビューについては別記事を参照してください。
事例研究のポイント2:事例に根差した分析をする
看護学研究における事例研究の学会発表などでよく目にするものとして、ある事例を既存の理論に当てはめて分析したものを目にすることがあります。研究の目的によっては、既存の理論に当てはめて分析することが必ずしも悪いというわけではありませんが、適切とは思えないものも少なくありません。第一に、理論の使い方が不適切なものが多いです。これは「理論」というものに対する理解不足に起因していることが多いのですが、今回は長くなるため割愛します。第二に(これが最も残念なことなのですが)、ポイント1で説明したように、取り扱うテーマがこれまでにない特異的なものであるにも関わらず、事例(データ)を既存の理論に当てはめて分析することで、その特異性が失われてしまっていることです。そのテーマが特異的なものであれば、やはり事例もそのテーマに特徴的な結果が得られるはずです。既存の理論に、半ば無理やり当てはめることによって、その特徴が失われた、どこかで聞いたような結果だけが並べられた研究になってしまいます。
こうした事態を避けるためには、やはり事例(データ)に根差した分析をするべきです。すなわち、事例(データ)を分析する際は、既存の理論や過去の研究結果はいちど忘れて、その事例(データ)から純粋に結果を導くべきなのです。この作業はすんなりとできるものではなく、悩みながら、ときに暗中模索しながらの分析になります。ついついそんな時に、既存の理論枠組みや過去の研究結果を頼りにしたくなるのですが、その誘惑に負けてしまうと、先ほどの例のようにテーマの特徴(新規性)が失われてしまいます。あくまで事例(データ)はどのようなプロセスを経たのか、どのような概念が抽出されるのか、そこに根差した分析を行うことで、テーマの特徴を反映した結果が得られるはずです。既存の理論や過去の研究を使うのはそのあと、考察で存分に使いましょう。今回得られた特徴的な結果は、既存の理論と過去の研究と比べて、何が同じで何が違うでしょう?それらを論じるのが、研究の「考察」です。
事例研究のポイント3:研究の目的を明確にする
これも他の研究手法を用いた研究と同じですが、時として事例研究は、目的を見失い(あるいはもともと目的が不明瞭)、単なる物語になってしまいがちです。私たちが行おうとしているのは、ノンフィクションを書くことではなく「研究」をすることです。研究がノンフィクションにならないためには、明確な研究目的を設定し、それを見失うことなく分析してまとめることが重要です。
研究の目的は研究疑問(Research question)に依存します(RQの立て方は別記事を参照してください)。研究を通して、何を明らかにしたいのでしょう?対象者の心理や認識のプロセスでしょうか?あるいは家族の疾患の受け入れプロセスでしょうか?自宅療養に必要な手技獲得に必要な医療者の支援方法でしょうか?ひとつの研究で、たくさんのことを明らかにすることは難しいです。したがって、自分たちが何を明らかにしたいのかという目的を明確にし、事例(データ)をその目的に照らし合わせながら分析していくことで、不要なデータを拾うことなく、必要なデータを抽出することができます。研究の目的、すなわちこの研究で明らかにしたいことが明確になっていない研究は、結果や考察を見ているとすぐにわかってしまいます。研究の目的が不明瞭なまま分析したであろう研究は、結果に一貫性がなく、事例研究の良さが失われていることが多いです。例えば、退院指導における患者の手技獲得プロセスに着目したテーマだったにも関わらず、家族の認識が色濃く結果に反映されていたり…。研究の目的(明らかにしたいこと)に関連しないデータを拾ってしまったり、逆に関連するデータを見落としてしまったりしないよう、あらかじめ分析前に研究の目的(研究で明らかにしたいこと)を明確にしておきましょう。
事例研究のポイント4:現象(事例)を深く理解すること
ポイント3の冒頭でも触れましたが、事例分析が単なるノンフィクションにならないようにするためには、「なぜその現象が起きたのか」を深く理解する必要があります。なぜ看護師のある関わりが対象者に効果的だったのか、対象者に効果的だった関わりはなぜ特定のある介入だったのか、なぜ対象者はそのような反応をしたのか、など、事例を深く理解していくことが重要です。そのためには、事例データの表面だけをただ眺めているだけでは、その現象の本質的な理解にはつながりません。現象(事例)を深く理解するためには、現象(事例)に対して常に「なぜ?」と問い続けることで見えてきます。私が事例研究をする際は、現象(事例)に対してインタビューしている気持ちで事例を読み解いています。まるで現象(事例)と半構造化面接をしているかのように。そのくらい深く事例を理解することで、そのテーマに特徴的な結果が得られるのです。
そして、現象(事例)に対し「なぜ?」と問い続けるのと同じくらい重要なこととして、結果をまとめる際は常にデータからその目的につながるような情報をもとにまとめるということです。事例に深く入り込んでいくと、時として研究者が持つ先入観や既存の情報に当てはめて事例を理解しようとしてしまいます。それは適切な分析とは言えません。問いかけた「なぜ?」に応えてくれるようなデータを事例の中から読み解くことで、事例を深く理解しテーマに即した結果を得ることができるのです。
事例研究は(他の研究手法も同様ですが)、研究者の問いと研究目的によって、事例の読み解き方や着眼点、分析方法など具体的な研究遂行プロセスは多種多様です。主たる研究者だけで研究を進めるのではなく、適宜仲間やスーパーバイザーの力も借りながら、テーマに特徴的な結果を導いてほしいと願います。